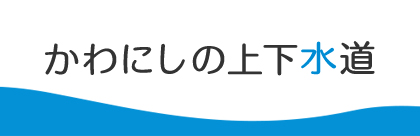令和7年 第3回川西市議会 一般質問

ふくにし 勝
今回は「マンホールを活用した下水道事業の啓発」、「小学校における運動の機会の確保」、「川西市立総合体育館の大規模改修」についての一般質問を行いました。
質問1.マンホールを活用した下水道事業の啓発について

① 下水道事業啓発に対する市の考えについて
9月10日は下水道の日であり、9月10日に一般質問をしました。
下水道は地下に埋設されているため、市民が目にすることはありません。
雨水ポンプ場や汚水ポンプ場の周辺に住まれている市民はその存在を知っていても、多くの市民は何の施設か知らずに日常生活を送っています。
しかも猪名川流域下水道原田処理場は豊中市にあることから市民の関心は薄いのかも知れません。
蛇口をひねればおいしい水が飲めて、当たり前のようにトイレやお風呂を利用できる。
今までは当然のことではありましたが、近年の道路陥没などで市民は当たり前ではないことに少しずつ気づきだしています。
だからこそ9月10日の下水道の日以外でも、更なる下水道の啓発活動を進めていただきたいと考えます。
② マンホールを活用して、啓発の一歩とする考えについて
1.市民などから寄贈を受けて、設置する考えについて
例えば、子どもや孫の描いた絵をマンホールにすることや、ご自分の描かれた絵や習字、カメラで撮った写真などをマンホールにすることが考えられます。
下水道について考えてもらえるきっかけになる上、自分の大切なものがいろんな人の目に留まる効果が考えられます。加えて工事費用が削減される効果もあるため提案しました。
ただ、地面にあるので踏まれたりすることで抵抗があるかも知れませんが、メジャーリーグベースボール(MLB)は2025年6月16日から29日にかけて日本人メジャーリーガー12選手の特製マンホールを出身地に設置されました。
また自治体独自にメジャーリーグ日本人選手のステッカーを配布されているまちもあります。
マンホールを街のブランディングづくりに活用することを提案しました。
2.民間事業者などから広告スペースとして、活用してもらう考えについて
マンホールで稼ぐ時代になりました。
平成30年に日本で初めて埼玉県所沢市の上下水道局において「マンホール蓋有料広告事業」が開始され、令和元年度には愛知県豊川市、令和2年度には神奈川県小田原市、大阪府枚方市と続いて同様の事業が開始されています。
現在では大阪府豊中市や高槻市、寝屋川市、大東市でも既に実施されています。
マンホール蓋の広告事業発祥の地、所沢市では夜に光るイルミネーションマンホールが導入されています。
もちろん自治体の負担はありません。
こうした事業を学ぶため先日、高槻市へ視察に行きました。
令和6年度に6箇所のマンホールを広告収入とされていました。
令和7年度には新たに 17箇所増えて11月1日には合計23箇所となるそうです。
高槻市は、下水道事業会計が赤字経営になることが確実となり、市民への下水道料金値上げの前に担当課としてできることを模索した結果、歳入増を目的としたマンホールを広告として活用する経緯があるとのことです。
職員さんのたゆまぬ努力を感じられた視察となりました。
デザインマンホールの公募も含めてマンホールを広告として活用する時代になった、自治体の危機感の表れと推察します。
川西市においてもマンホールを広告として活用することを提案しました。
③ マンホールカードの作成について
川西市は3種類のマンホールカードを作成しましたが、現在は1種類も配布されていません。
近隣自治体の猪名川町や伊丹市、池田市、箕面市などの阪神間、北摂地域の多くの自治体では絶賛配布中です。
関係人口を増やすためにも、今あるマンホールカードの再版若しくは新規作成をするべきと提案しました。
質問2.小学校における運動の機会の確保について

① 体育の授業や休み時間の現状について
新型インフルエンザの影響もあり、子どもたちの運動不足が原因で、体力が低下していると言われています。
暑かった夏が終わろうとし、スポーツ・文化・芸術の秋に向かおうとしています。
近年はスマートフォンの普及によって手軽にゲームができる時代となりました。
暑い日や、雨の日に屋外で体を動かすことは難しいですが、晴れた日やこれからの季節は屋内・屋外を問わず、大人も子どもも体を動かせる環境を整備することは自治体の役割と認識しています。
特に子どもにとっての運動習慣の形成はとても重要と考えます。
② ニュースポーツの取り入れについて
1.テニピンを体育の授業に取り入れる考えについて
テニピンはテニスをより手軽に誰もが楽しめるように開発された新しいスポーツです。
バドミントンのコートの大きさで、真ん中に高さ約80cmのネットを置き、ラケットの代わりに手の平より大きなスポンジや段ボールを貼り合わせたハンドラケットを手にはめ、スポンジボールを打ち合います。
日本テニス協会が推薦し、文部科学省では2017年改定の小学校学習指導要領、解説体育編にもバドミントンやテニスを基にしたやさしいゲームが例示されています。
川西市としても体育の授業に取り入れて、子どもたちにボール遊びの楽しさを知ってもらうことを提案しました。
2.手打ち野球の普及について
私の体験談にもなりますが、親世代の男性は野球をしていることが当たり前の時代でしたが、今は違います。
たくさんのスポーツができる環境は選択肢が増えて、その人に合ったスポーツに出会える今はとても素晴らしい時代になったと思います。
しかし野球人口の減少は個人的にとても寂しく危機感を持っています。
手打ち野球はバットやグローブを使わずに素手で柔らかいボールを打ち、守る野球を基にした遊びです。
しかしながら、手打ち野球にも日本代表が2024年3月に発足していまして、侍ジャパンBaseball5として活動しており、男女混合5人制の「Baseball5」という競技があります。
15歳から18歳までのアスリートを対象の2026年夏季ユース五輪がセネガルのダカールで開催されますが、この大会でBaseball5の採用が決まっています。
またBaseball5は将来の五輪競技採用を目指しています。
手打ち野球もテニピンと同じように小学校の授業で行っていただくよう要望しました。
質問3.川西市立総合体育館の大規模改修について

1.大規模改修の詳細について
川西市立総合体育館は来年度から大規模改修が予定されています。
その詳細設計委託料として令和7年度予算に4,300万円が計上されました。
トイレ改修やエアコン整備など改修する内容はたくさんあると思いますが、現状機能を維持するための改修工事の確認ができました。
そこで日頃より市民の皆さんからいただいた意見として、第2体育室と第1武道室のエアコンの新設や第1体育室のフローリングへの整備、女子トイレの洋式を増やすこと、駐輪場の整備を提案しました。
また、市民体育館は旧体育館と新体育館ともに入口で下履きから上履きに履き替えていますが、総合体育館は曖昧なところがあり、特にトイレや更衣室は上履きと下履きのどちらでも可能となっている点で、衛生的な観点から利用者の指摘を意見しました。
大規模改修をそのタイミングとして見直すよう提案しました。
2.一時休業期間の周知の状況について
保健センターは運営をしながらの改修工事でありますが、総合体育館は使用停止しての改修工事と聞いています。
2026年夏頃から2027年3月頃まで使用できなくなることから、市民やスポーツ協会の加盟団体へ周知を詳細が決まった段階でしていただくようお願いいたしました。

川北 将
9月定例会では「空き家等の解体費用に関する助成・支援について」と「交差点や通学路における歩行者の安全確保について」を質問しました。
全国的に空き家問題は深刻化しており、老朽化住宅の倒壊・火災リスクは地域の安全に直結します。国は法改正により管理不全空家への指導・勧告を強化しましたが、解体費用が高額なため所有者の自発的な除却を促す仕組みが必要です。
川西市では2018年に「空家等対策計画」を策定、2024年には「空き家対策・マンション管理適正化推進計画」を策定し、空き家マッチング制度やリフォーム助成、耐震化補助などを実施してきました。私からは、「解体して通学路の安全確保に役立てたいが費用負担が大きい」と市民の声を紹介し、制度的後押しの必要性を訴えました。
交通事故、とりわけ交差点事故の防止は喫緊の課題です。歩車分離信号は全国的に普及していますが設置率は5%にとどまります。2025年には警察庁が設置基準を緩和し、死亡事故や事故多発が確認されれば地域の要望なしでも設置検討可能となりました。
川西市では2023年に県内最多事故を記録した「小花1丁目交差点」が問題視されています。市単独での信号設置権限はありませんが、県警や公安委員会と連携し、歩車分離式信号の導入を含めた安全策を求めました。
質問1.空き家等の解体費用に関する助成・支援について

1.空き家マッチング制度の成果と課題について
2020年開始。官民・専門家が参画し、所有者と活用希望者をつなぐ仕組み。登録件数は年ごとに増減があり、成約は年数件にとどまります。課題は周知不足や活用に至らなかった事例の存在であり、成功例と併せて公開すべきと提案しました。
2.空き家活用リフォーム助成、耐震化促進補助制度の取り組み状況と今後について
若年・子育て世帯の定住を促す制度として一定の効果を上げましたが、令和7年度分は既に予算上限に達しています。需要が高く、県への予算要望などが必要です。
3.空き家等の解体費用を支援する考えについて
現時点で本市は解体費用の直接助成制度はなく、2025年度予算では「老朽危険空き家除却支援事業補助金」として予算計上されていますが、私からは跡地を公共活用する場合に除却や敷地再編を支援する制度の必要性を訴えました。
質問2.交差点や通学路における歩行者の安全確保について

1.交通事故多発交差点における対策について
2024年度より警察・県・市が「交通安全対策連絡会議」を設置し、事故要因分析と重点交差点の選定を実施。2025年度は6交差点が対象となっています。私からは小花1丁目交差点の対策として、渋滞リスクを考慮しつつ右左折車両分離方式の採用を提案しました。
2.交差点における歩行者の安全確保の取り組みと課題について
本市では交差点のカラー舗装や街頭啓発やパトロール強化などソフト対策が進められています。私からはAIカメラ等のデジタル技術を活用したデータ分析による安全対策を提案しました。
3.通学路における歩行者の安全確保の取り組みと課題について
合同通学路点検や従来からの見守り活動、市内全域の中学生と保護者が参画した川西市ヒヤリハット体験マップが公開されています。
最後に、歩車分離信号の契機となった1992年の児童死亡事故より「信号はなぜあるのか。事故にあわないため」という亡くなられた子どものカードを紹介しました。従来の見守りに加え、信号制御による歩車分離を進めること、またデジタル技術やAI活用を通じて市として子どもの通学の安全を守ることを訴えました。

中井 なりさと
「自然学校の見直し」や「中学校給食における”パン導入“の検討」について一般質問を行いました。
質問1.自然学校の見直しについて

1.自然学校の意義と現状
兵庫県の誇る教育プログラムである「自然学校」は、平成3年度より始まり、県内すべての小学5年生を対象に4泊5日の日程で実施されてきました。
子どもたちは家庭や学校を離れ、豊かな自然の中で集団生活を行うことで、自律性や責任感、協働の力を育むことができます。学校の教室では得難い学びの場であり、大変意義深いプログラムであることに疑いはありません。
一方で、近年はその実施に伴う「負担の大きさ」が大きな課題となっています。学校現場からは業務過多、保護者からは準備や費用の重さ、子どもたち自身からも体力的・心理的な負担が指摘されています。
2.学校現場の課題
(1)教職員の負担
- 4泊5日の実施には数か月前からの詳細な計画・調整が必要で、担任を中心とする教職員に大きな業務負担が発生。
- 当日の引率、夜間対応、体調管理は心身への負担が大きい。
- 兵庫県の実施要項で「教員の引率は原則2泊3日まで」と定められており、途中で交代が必要。結果的に他学年の授業や校務にもしわ寄せが生じている。
- 小規模校では担任が2泊3日で一度帰り、その後は日帰りで現地に通う事例もあり、子どもにとっても教員にとっても望ましい形とは言えない。
(2)働き方改革の観点
自然学校直前の数週間は、事前準備・打ち合わせで極めて多忙となり、働き方改革の趣旨とも逆行する実態がある。
3.保護者の課題
数泊分の衣類や持ち物の準備が必要であり、専用鞄の購入など経済的負担が生じている。
- 食費・持ち物準備を含め、4泊5日で数万円規模の支出になる家庭もある。
- 「楽しい体験」と評価する声がある一方で、「体力の低下」「デジタル依存傾向」などから4泊5日は過重ではないかとの不安も強い。
- すべての子どもが参加できているわけではなく、不参加児童への不公平感も課題となっている。
4.子どもたちの課題
- 長期宿泊に伴い、体調不良やホームシックが3日目以降に顕著となり、学びに集中できない例も報告されている。
- 障がい、アレルギー、母子分離の難しさなどから、参加できない児童が発生している。結果として「全員参加」の理念が揺らいでいる。
5.実施日数の見直しについて
神戸市はすでに「2泊3日」への短縮に踏み切りました。教育効果を損なうのではないかという懸念に対して、神戸市教委は「質は十分確保できる」と説明しています。
短縮により、以下の利点が考えられます。
• 教職員の業務負担軽減
• 子どもたちが疲弊する前に体験を凝縮できる
• 荷物や費用負担が軽減され、より多くの子どもが参加しやすくなる
つまり「量より質」への転換こそが時代に即した自然学校のあり方といえます。
6.都市部と県北部の違い
- 都市部(阪神間):自然体験が少なく、長期宿泊や荷物準備を「大きな非日常」として負担に感じやすい。移動距離も長く、学校規模が大きいため調整が複雑。
- 県北部(丹波・但馬):自然が身近で、泊まり経験も豊富。移動距離が短く、小規模校が多いため調整しやすく、長期宿泊にも抵抗が少ない。
地域による受け止め方の違いを前提に、制度を柔軟に運用できる仕組みが求められます。
7.市としての今後の対応課題
- 現場の声の丁寧な把握:子ども・保護者・教職員それぞれの負担を市教委として明確に認識すること。
- 県への働きかけ:市町の裁量拡大や制度の柔軟化を求めていくこと。
- 市の独自支援:もし短縮によって県補助金が減額された場合、市として財政的に補完する姿勢を示せるかどうか。
8.まとめと要望
自然学校は子どもにとってかけがえのない学びの場であり、その価値を否定するものではありません。しかし「30年前の形」をそのまま続けるのではなく、時代の変化に即した見直しが不可欠です。
• 教職員の働き方改革と安全管理の観点
• 保護者の経済的・時間的負担の軽減
• 子どもの多様性に対応した「全員参加」の実現
これらを踏まえ、川西市としても「柔軟で持続可能な自然学校」の実施に向けた検討を進めるよう、強く要望いたします。
9.教育長答弁
- 自然学校を通じて、子どもたちは体験を積み重ねており、教職員にとっても教育的な手ごたえを感じる場面は少なくない。
- 近年の課題の背景には、少子化に伴う学校規模の縮小があり、これが負担を生じさせる一因となっている。
- 自然学校の運営にかかる負担は、学校規模によって様々に分かれる。
- 市としては、各学校の実情に応じて宿泊日数を選択できるよう、県に対して制度上の柔軟性を求めています。
- 自然学校は県の「看板事業」と位置付けられており、現時点では4泊5日という実施形態は譲れない。
- 2030年の学習指導要領改訂に向けて教育課程全体の見直しを進める中で、自然学校のあり方についても改めて検討したいと思っている。
質問2.中学校給食における「パン導入」の検討について

本市の中学校給食は、令和4年9月から「完全米飯給食」を掲げて実施されています。その一方で、令和6年度末には生徒からの要望を受け、「パンを試行的に導入する」との方針が教育委員会から示されました。しかしその後、PTA連合会から「拙速に進めるべきではない」との請願が提出され、議会で採択された結果、導入はいったん見送られることとなりました。
ただし、同じ市内の小学校給食では、月に1回程度のパン提供がすでに行われています。つまり「パン」という食材そのものが学校給食にふさわしくないと判断されたわけではなく、あくまで中学校における運用上の課題が理由で見送られたにすぎません。
私はこの議論を、単にパンを導入するか否かにとどめるのではなく、給食の在り方そのものを問い直す機会とすべきだと考えています。完全給食の理念をどう実現するのか。子どもたちの多様な食のニーズをどう受け止めるのか。そして保護者や地域とどのように協働していくのか。その過程こそが大切です。
実際に「パンを食べたい」という子どもたちの声に応える形で教育委員会が動いたことは、大変意義深いことでした。子どもの声が教育行政を動かしたという事実は、それ自体が貴重な学びにつながります。その後に実施されたアンケートでも、導入に前向きな意見が多数示されたと承知しています。今後は、アレルギー対応を含む安全面に十分配慮しながら検討を深めていくことが望まれます。
ここで強調したいのは、給食の意思決定にあたり「本末転倒」になってはならないということです。理想や形式にとらわれすぎて、結果的に子どもたちが食べ残しを増やし、食材を無駄にしてしまうようでは本来の目的が失われます。また、通常の献立づくりにおいても、意思決定の根拠が一部の声に偏っていないかを改めて確認する必要があります。給食の在り方は、一握りの意見だけでなく、今を生きる子どもたちの率直な声を正面から受け止め、反映させていくことによってこそ、本来の教育的な意味を持つものになるはずです。
残食の問題にしても、子どもたちの意見を取り入れることで改善できる余地があります。現在は「ご飯に合うおかず」という前提で献立が組まれていますが、それが子どもたちの嗜好と必ずしも一致せず、食べ残しにつながっている現状があります。食文化の継承は大切ですが、子どもたちが「おいしい」と感じ、しっかり食べきってこそ教育的効果を持ちます。
給食は単なる栄養補給にとどまらず、子どもたちが自ら意見を表明し、その声が仕組みを変えていくという民主的な学びの場でもあります。だからこそ、子どもたちの声を丁寧に受け止め、より反映した形で給食の改善を進めていくことが求められます。
私は、今回のパン導入をめぐる議論をきっかけに、本市が「子どもの声を軸とした給食づくり」へと一歩進むことを強く望みます。完全給食の理念を尊重しながらも、多様なニーズに応える柔軟な仕組みを整え、残食の削減と食育の充実を両立させる。その実現に向けて、保護者や地域と協働しながら丁寧な議論と準備を進めていただきたいと考えています。