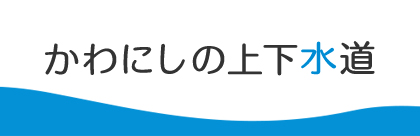令和7年 第2回川西市議会 一般質問

中井 なりさと
「ギャンブル依存症」や「オンラインカジノ」は、もはや特別な人の問題ではなく、誰にでも起こりうる深刻な社会課題です。
家庭の崩壊、借金、児童虐待、自殺といった形で深刻化する前に、気づいて支える体制が必要だと考え、一般質問を通じて市の姿勢と対応を問いました。
ギャンブル依存症に対する市の認識と対応

質問ではまず、市がギャンブル依存症をどう認識しているのか、その基本姿勢を伺いました。
現在、川西市にはギャンブル依存症の明確な相談窓口は設けられておらず、「対応できていないのが現状」との答弁がありました。一方で、「今後は前向きに取り組みたい」との回答もあり、一定の方向性が示されたと受け止めています。
質問と要望を交えて訴えたこと
- 市の中に「相談窓口」を設けるべき
「県と連携を」との答弁がありましたが、川西市民にとって“県”は遠い存在です。
福祉の一部ではなく、市全体で取り組むべき課題として位置づけ、市として明確にギャンブル依存症相談窓口を設けるべきと要望しました。 - 当事者の声を活かした啓発活動を
依存症は「自分とは関係ない」と思われがちです。そこで、当事者や家族の体験を取り上げた、心に届く啓発活動を提案しました。
5月にアステホールで開催された「ギャンブル依存症問題啓発週間セミナー」では、体験談がとても印象深く、強いメッセージとして伝わってきました。
このようなセミナーの市内開催や、市職員研修に当事者や支援団体の声を取り入れることを要望しました。 - 職員研修と相談対応力の強化を
まず「ここに相談できます」とはっきり示すことが第一歩です。
あわせて、職員が依存症についての正しい知識を持ち、適切な支援先へつなげられるようにするため、支援団体による職員向け研修の実施も求めました。 - 若年層への予防教育を
スマートフォンの普及により、子どもや若者がネットやゲームを通じて依存状態に陥ることが増えています。
学校現場での情報リテラシー教育の中に、依存症の予防を組み込むことを提案しました。
また、保護者向けの啓発講座や、生徒への出前授業など、家庭と学校が連携した取り組みが重要です。 - 支援団体との連携で相談環境を整備
実際に困っている方と、支援団体を市が窓口となってつなぐ仕組みが必要です。
明石市では、家族の会が市の相談窓口として定期的に相談対応をしています。
川西市でも、まずは家族の会等の支援団体に職員研修を依頼し、相談体制を整えていく流れを提案しました。
オンラインカジノ問題にも警鐘

オンラインカジノは、日本国内では明確に違法でありながら、スマホやSNS経由で若者を中心に広がっています。
「合法に稼げる」「簡単にできる」など、誤った情報が広まり、気づけば借金・依存・犯罪に至るケースも後を絶ちません。
オンラインカジノに関して要望したこと
- 市として違法性と危険性を周知する啓発の強化
- 教育・福祉・安全の各部署が連携した取り組み
- 相談窓口の明確化と「どこに相談すればよいか」の見える化
とくに若年層は、「遊び感覚」で始めてしまいがちです。
「知らなかったでは済まされない」社会的なリスクに対し、市が率先して啓発の声を上げることが必要だと訴えました。
市民を取り締まるのではなく、支える姿勢を
私の立場から一貫して訴えたのは、「市民を責める」のではなく、「市民を支える」行政のあり方です。
依存症の当事者も、その家族も、誰にも相談できずに孤立しています。
だからこそ、市が声を上げ、つなぎ、支える体制づくりが求められているのです。
市長の見解を求めました
今回の質問の最後には、市長に対して、ギャンブル依存症とオンラインカジノ問題に対する市としての見解と、今後の取り組みの方向性について明確にお聞きしました。
・非常に大切な課題であることを認識した
・市として具体的なアクションが必要だと思う
・窓口をどうするか等運用を考える
・具体的に一歩でも前に進んだなという形にしたい
・研修や子どもたちへの啓発等できるところをひとつずつやっていきたい。
との答弁をいただきました
この問題にどう向き合い、どんな施策を進めていくのか――今後の市の動きを注視してまいります。
今後に向けて
市民の皆さまの声を市政に届けるのが、私の使命です。
「こんなことで困っている」「こうしてほしい」など、ご意見・ご相談をいつでもお寄せください。
私たちのまち・川西が、誰もが安心して暮らせる地域となるよう、今後も粘り強く取り組んでまいります。

川北 将
6月定例会では「中学校の自転車通学の拡充について」と「災害時のトイレの確保について」を質問しました。
本市においては昨年2学期より清和台中学校・東谷中学校での自転車通学の試行がスタートし、自転車通学を認めてほしい声へ対応できた大きな前進だと捉えています。登下校に自転車通学が認められていないルールと地域クラブでは自転車移動が認められている中で、より時間を有効に活用できないのか、部活動の社会移行を見据えた中学校の自転車通学の許可について見解を伺いました。
阪神・淡路大震災から30年。当時は被災地の広範囲で水洗トイレが使えなくなり、避難所となった学校などのトイレが汚物であふれる状態になるなど、避難所のトイレの整備に様々な課題がありました。本市においても、今年度は防災体制を強化し、過去の災害の教訓を活かして防災・減災対策に今まで以上に取り組まれています。いつ起きてもおかしくない災害への備えとしてトイレの確保対策を進めなければならない視点で、市の取り組みを伺いました。
質問1.中学校の自転車通学について

- 部活動の社会移行を踏まえ、自転車通学を認める考えについて
- 自転車通学のガイドラインを地域クラブへの移動時にも徹底する考えについて
- 自転車に安全に乗るための取り組みと今後について
市の答弁
現在、清和台中学校と東谷中学校での試行実施を検証の上、その他の5つの学校について、段階的に拡大を図っていく。
また、部活動の社会移行に伴って、校区外への地域クラブへの移動が必要となる場合等では、自転車の通学をおこなうことで時間的な負担軽減や部活動の幅広い選択につながる。
本格実施に向けては、必要な安全対策を講じながら、通学の負担が比較的大きい地域の生徒や校区外の地域クラブに通う生徒等も対象として検討する。
地域クラブに通う際の自転車の利用の指導については、原則として地域クラブから生徒に一般的なマナーやルールを指導していただいている。保護者については、現時点では具体的な対応ができていない。
昨年度は警察や関係機関や関連部署に協力してもらい、試行実施校全生徒に交通安全講習会実施。また、民間企業と連携して新ヒヤリハットシステムを実施し、市HPに公開している。
今後も安全対策については、ソフト、ハード両面で工夫と検討を加えながら実施していく。
提案のあったスケアード・ストレイト交通安全教室も効果的な手段だと認識しており、今後実施していく安全教室の内容については、生徒と保護者の皆さんに意見をいただいていくが、ご提案の手法も含めて必要な情報を収集して検討を進める。
川北の意見
中学校の自転車通学のアンケート調査結果の分析や検証結果は今後となるが、生徒の状況に応じて自転車通学の利用を選択できるようにすることが必要ではないでしょうか。
部活動の社会移行を踏まえ、今後は一人ひとりに寄り添って自転車通学を認めていくことを進めていただきたいと思います。
あと、ハード整備では川西市自転車ネットワーク計画では2028年に100%整備を目指す計画となっている。部活動の社会移行や中学校の自転車通学(ちゃりつう)を踏まえ、元となるデータの再検証やハード整備を着実に進めていただきたい。
質問2.トイレの防災について

- 災害時のトイレの確保に向けた取り組み状況について
- 災害時のトイレ確保・管理計画を策定する考えについて
- 新設公園や跡地活用においてマンホールトイレを整備する考えについて
市の答弁
本市のトイレ備蓄数として、便槽式組み立てトイレ73基、ラップ式簡易トイレ15基、簡易トイレ58基の合計146基を備蓄している。
さらに、キセラ川西せせらぎ公園に貯留式マンホールトイレ20基、市民体育館に流下式マンホールトイレ5基を整備している。
トイレ備蓄数については、能登半島地震に派遣した職員からのヒアリングから、費用面・衛生面・女性への配慮を考慮し、排便処理セットと簡易トイレに見直すことで備蓄目標数を変更している。トイレの備蓄目標数については435基としており、令和12年度に目標備蓄数を達成する見込み。
備蓄しているトイレで対応が困難な場合には、民間のレンタル事業者との災害時応援協定により、不足するトイレを確保する仕組みを構築している。
現在、整備予定の旧市民病院跡地活用の公園では、防災機能を持たせる予定としているが、防災用トイレは下水管路の状況や想定避難者数により必要な設備を整備する方針。
今後、新設公園や跡地活用で防災機能を持たせることは、近隣避難施設の状況などにより、マンホールトイレの整備も含め、必要な防災機能を検討する。
川北の意見
この質問をするきっかけになった市民の声として「新しく公園をつくるならトイレやマンホールトイレを整備できないか」という声でした。
日本トイレ研究所が行ったアンケート調査によれば、「災害時に自宅の水洗トイレが使えなくなった時にどうするか」という問いに対して避難生活を自宅で送りたい人の44%が「避難所のトイレを利用する」「公園や公衆トイレを利用する」と回答しており、備蓄している災害用のトイレを利用するとした人はわずか15.6%でした。
また、日本トイレ協会の調査によれば、自宅に災害時用のトイレを備蓄している割合は、22.2%となっています。まだまだ2割。自助でのトイレの備えは足りていない状況です。
市の備えも限りがありますし、例えば下水道が使えなくなったとき、マンションなどは下水道が損傷している中で汚水を流すと1階が汚水であふれてしまう可能性があること等を考慮すると、各家庭で携帯トイレを備蓄していただく、こういったメッセージを発信しつづけていくことが大事かと思います。そのためには、市全体のトイレ確保・管理計画がまずは必要。
災害時に水道、電気、ガスが使えなくなっても、トイレはすぐに必要になります。
市民、地域、市のそれぞれが重要性と役割を認識し、災害時のトイレ確保に取り組んで行くことが安心できる避難地の整備につながるのではないでしょうか。
引き続き、私自身も災害時のトイレのあり方や必要性を周りに伝えてまいります。

ふくにし 勝
今回は「個人市民税における更なる詳細の公表」と「川西市立中央図書館の今後」についての一般質問を行いました。
質問1.個人市民税における更なる詳細の公表について

個人市民税における更なる詳細の公表についてでありますが、令和7年度一般会計予算審査の賛成討論でも言わせていただきましたが、固定資産税や都市計画税を含む様々な税収の積算根拠は国で決まっており川西市で変更することはできないと認識しています。
しかし、個人市民税や法人市民税の均等割は自治体で変更することは可能と認識しています。
川西市の税収は個人市民税が市税の45.5%ととても大きな割合であり、予算決算においても様々な議論がされていますが、収納率や滞納状況等と毎回同じ内容の質問が行われています。
徴収業務は大切なことではありますが、そのこと以上に個人市民税の詳細を公表していくことも大切なことと認識しています。
例えば東京都三鷹市においては個人市民税の内訳を詳しく調査し公表されています。
現状把握を行い今後の推移を予測することはとても重要と認識しています。
今後の個人市民税額の推移について
人口が減少していくので納税者も減少し、個人市民税額は減少していくことも想定されます。
しかし現役世代の所得が増えると個人市民税額は増えると認識しています。
そのような観点から国は最低賃金の上昇を含めた所得の向上を進めています。
ただ、所得が増えても社会保障の負担が所得以上に増えていくので手取りが増えている実感が少ない状況は今後も続くと推察します。
年齢別の個人市民税額と年齢別一人当たりの平均個人市民税額の公表について
例えば、生産年齢人口の納税額の割合が高いのか低いのか。
年金所得の納税者数が何人で、多いのか少ないのか。
納税者の人数と納税額だけでは現状把握は何もできません。
個人市民税の内訳を詳しく精査することで現状把握ができると考えます。
令和8年度には自治体情報システムの標準化が進み、そのタイミングで整備されると願います。
質問2.川西市立中央図書館の今後について
川西市立中央図書館の開設は平成3年4月12日にアステ川西内に整備されました。
開設後34年以上が経過しています。
アステ川西や川西阪急は大規模改修が行われリニューアルされました。
これらは、今後20年・30年後を見据えた今のタイミングであったと推察いたします。
しかし川西市立中央図書館は開設以来、災害時に復旧工事がおこなわれましたが、大規模な維持管理はエレベーター改修と認識しています。
また本年1月16日には5階調査相談室の天井から水漏れがありました。
新図書館の整備について
みつなかホールの大規模改修が終了し、今後は川西市立総合体育館や川西市民温水プールなど様々な施設の老朽化が進んでいる中、川西市立中央図書館の新設は川西市の財政上厳しいからこそ、川西市立中央図書館の大規模改修は必要と考えます。
大規模改修について
令和5年度は川西市立中央図書館に授乳室が整備されました。
また全9公民館の図書室の蔵書を含む全ての本にICタグを設置し、全9公民館とオンラインで繋ぐことで、どこの公民館でも貸し借りができるようになりました。
時代の変化に合わせて利用しやすくなったように受け止めます。
しかし事務所の中や貸し借り時に市民が利用する受付の壁紙は剝がれていて、阪神淡路大震災の影響で壁に亀裂が残ったままであります。
床も含めた改修工事が必要です、また本棚のレイアウトの変更が必要で、開館時から同じレイアウトとなっています。
その他にも何も活用されていないバルコニーの有効活用を提案しました。
そして開館時にあった出入口の再稼働についてはシャッターが閉まったままとなっているため検討のお願いしました。